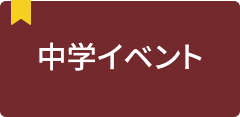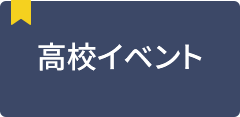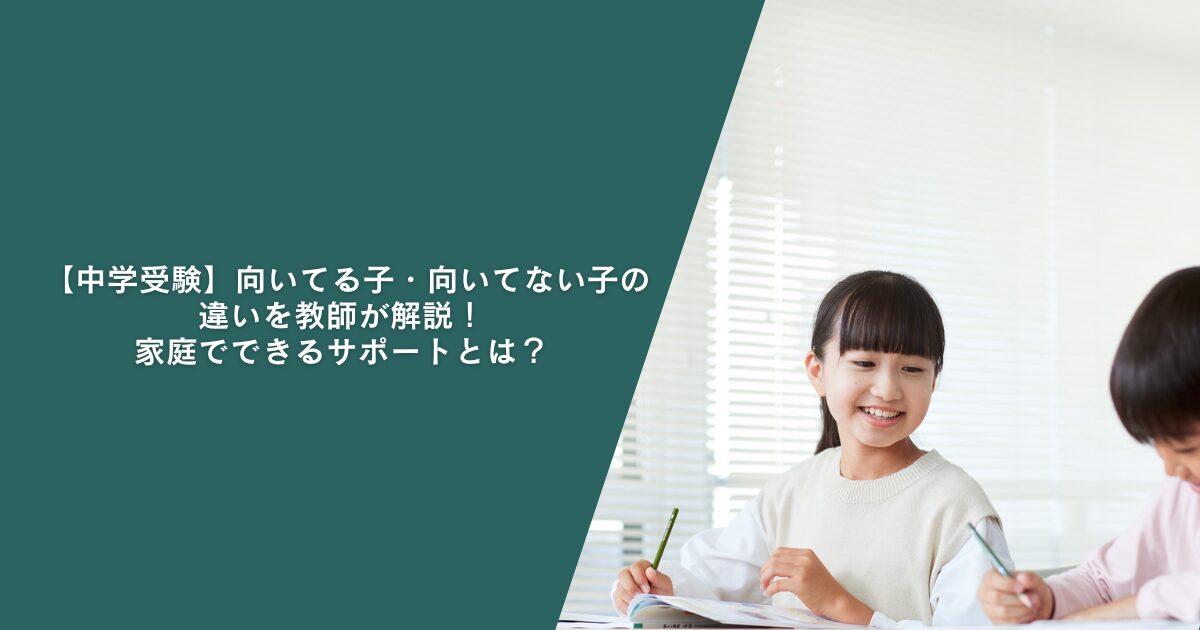
【麗澤瑞浪中学・高等学校監修記事】
「うちの子、中学受験に向いてるのかな……?」
お子さんの適性について不安を感じている保護者の方は少なくありません。
この記事では、中学受験に向いている子・向いていない子の特徴を、麗澤瑞浪中学・高等学校がわかりやすくご紹介します。
ただし、向いていない特徴があるからといって、すぐに「うちの子には無理かも…」とあきらめる必要はありません。
大切なのは、お子さんのタイプを知った上で、その子に合った学び方やサポートを見つけることです。
後半では、受験対策を始める時期の目安や、保護者が家庭でできるサポートについてもご紹介します。
中学受験に向いている子の5つの特徴

「うちの子、中学受験に向いているのかな?」
そう感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。
中学受験に向いているかどうかを考えるときは、まず「どんな子が向いているのか」を知ることが大切です。
ここでは、中学受験に向いている子どもの特徴を5つご紹介します。
お子さんに当てはまるところがあるか、チェックしてみてくださいね。
勉強することが好き(コツコツ型)
「勉強が大好き!」というお子さんは少ないかもしれませんが、実は中学受験に向いている子には「ちょっとした好き」があることが多いんです。
・とにかく本を読むことが好き
・算数のパズル問題を解くのが楽しくて好き
・地図や資料集をながめるのが面白くて好き
このように、何かひとつでも「好きな勉強」がある子は、他の教科にも自然と興味を広げていく可能性があります。
また、中学受験では「コツコツと毎日勉強を続ける習慣」もとても大切です。
とはいえ、最初から自分で勉強を続けられる子はほとんどいません。
小さいうちは、保護者の方が毎日のペースづくりをサポートしてあげることで、少しずつ習慣が身についていきます。
このように、「学ぶことに前向き」で「コツコツ取り組める」子は、中学受験にとても向いているといえるでしょう。
自立している(自分で計画を立てられる)
中学受験では、「自分で考えて行動する力」がとても大切です。
たとえば……
・親が言わなくても宿題に取りかかる
・ゲームの時間を自分で調整できる
こんな行動ができる子は、自分をコントロールする「自立心」が育ってきている証拠です。
中学受験では長期間の勉強が必要になるため、自分で計画を立てて取り組む姿勢が大きな力になります。
とはいえ、小学生のうちに完璧に自立できている子は多くありません。
自立心は受験勉強を通して少しずつ育っていくものです。
低学年のうちから、子どもが「自分で考えて動けるようになる」ように、保護者の方が少しずつ声をかけてサポートしてあげると安心ですね。
受験に対して明確な目標がある
「どうしてこの学校に行きたいのか?」という明確な気持ちを持っている子は、中学受験にとても向いています。
たとえば以下のような行きたい気持ちがある子にはおすすめです。
・「〇〇中学校でこの部活をやってみたい!」
・「あの学校の制服に憧れている!」
・「将来の夢のためにこの学校の教育が必要だと思う」
どんなきっかけでも「行きたい理由」がある子は、長期間の受験勉強にも前向きに取り組みやすくなります。
中学受験は「なんとなく」で乗り越えられるものではありません。目標があることで、日々の勉強にも意味が見いだせるようになり、自分から学ぼうとする姿勢が自然と育まれていきます。
途中で壁にぶつかっても、「あの学校に行きたい!」という強い気持ちが支えになってくれるはずです。
知的好奇心が高い(新しいことを知るのが楽しい)
「どうして?」「なぜ?」と疑問を持つ子は、学ぶことを楽しめるタイプです。
新しい知識に出会ったときにワクワクできる、そんな好奇心旺盛な子は中学受験にとても向いています。
たとえば……
・「この植物はなぜこんな形なの?」
・「昔の人ってどんな暮らしをしてたの?」
・「地図を見て、ここに行ってみたい!どんなところなの?」など
こうした疑問を自分から調べてみたり、誰かに聞いてみたりする子は、自然と学ぶ習慣が身につきやすくなります。
また、ただ暗記するだけでなく「理由を考える」「仕組みを理解する」力が育つため、思考力を問われる応用問題にも強くなります。
「勉強=つらいもの」ではなく、「勉強=新しい発見がある楽しい時間」と感じられる子は、受験勉強でも前向きに取り組めるはずです。
精神年齢が高い(落ち着いている)
中学受験は、小学生にとって初めて本格的な「競争」に向き合う場面でもあります。
模試の結果に一喜一憂したり、本番が近づくにつれて不安になったり……。子どもにとっては大きなプレッシャーがかかるものです。
そんな中でも、以下のようなタイプの子は、受験においてとても有利です。
・感情の起伏が少なく冷静に行動できる
・緊張しても気持ちを切り替えられる
・落ち着いて物事に取り組める
精神的に安定している子は、プレッシャーに流されにくく、自分のペースで学習を進めることができます。
結果が思うように出なかったときも、前向きに切り替えて努力を続けられるのです。
こうした「心の強さ」や「自己管理の力」は、受験だけでなく、これからの人生でも大きな武器になります。
中学受験に向いていない子の特徴

中学受験に「向いていない」と聞くと、少し不安になってしまうかもしれませんが、ここでお伝えするのはあくまで「今の時点での傾向」です。
大切なのは「勉強が得意かどうか」ではなく、「受験勉強のスタイルに合っているかどうか」。中学受験は、ある程度の自己管理や集中力が求められるため、その特性にフィットしにくい子もいます。
ここでは、中学受験にやや不向きとされる特徴を紹介します。
とはいえ、これらの特徴があるからといって「中学受験は無理」というわけではありません。
環境や保護者のサポートによって、子どもはどんどん成長します。
今のお子さんの様子と照らし合わせながら、できることから少しずつ整えていけたらよいですね。
自発的に勉強することが苦手(やる気が続かない)
中学受験では、ある程度「自分から勉強に取り組む姿勢」が求められます。
・言われないと宿題をやらない
・気分が乗らないと手が止まってしまう
・やる気の波が大きい
このように、集中力がない子、勉強に苦手意識のある子、自発的に勉強を始めるのが苦手な子は、長期間にわたる中学受験の勉強を続けるのが難しいケースがあります。
特に親が常に声をかけて勉強を促す必要があると、保護者側の負担も大きくなり、親子共にストレスを感じやすくなってしまいます。
ですが、「勉強へのやる気」はトレーニング次第で少しずつ育っていきます。
最初は5分でも構いません。「机に向かう習慣」をつくることから始めてみましょう。
成功体験を積むことで、自分から学ぶ力も徐々に育っていきますよ。
受験の目的や目標がはっきりしない
「なんとなく受験する」「親に言われたから受ける」というように、受験の目的や目標が曖昧なままだと、勉強への意欲が続きにくくなる傾向があります。
・志望校への具体的な憧れがない
・入学後に何をしたいかイメージできていない
・自分自身で「受験する理由」を持てていない
このような状態では、受験勉強を続ける中で「本当に行きたいの?」という迷いが出てきてしまうことも。
中学受験を成功に導くには、「なぜその学校を目指すのか?」という目的意識が大切です。
保護者の方も、お子さんと一緒にその理由を見つけていく時間を持ってみてください。
パンフレットを見たり、学校見学に行ったりする中で、「ここに行きたい!」という気持ちが芽生えるきっかけがつかめるかもしれません。
文字を書くのが苦手で記述問題に苦戦しがち
中学受験では、算数・国語はもちろん、理科や社会でも記述式の問題が出題されます。
そのため、文字を書くことが極端に苦手だと、得点に影響する場面も出てくるでしょう。
最近はタブレット学習やタイピングの機会が増えてきて、手書きの文字に触れる時間が減っている子も多いですよね。
その分、「書くこと=面倒くさい」「すぐ手が疲れちゃう」と感じやすい傾向もあります。
もしお子さんが「書くこと」に苦手意識を持っている場合は、少しずつ慣れていくことが大切です。
たとえば……
・「1分でどれだけ書けるか」などゲーム感覚で楽しく練習する
・マス目ノートを使って、字のバランスを意識しながら書いてみる
・太めの鉛筆やグリップを使って、手に力が入りやすいよう工夫する
書くことへの抵抗感が少しでも減ると、記述問題への自信にもつながります。
「上手に書くこと」よりも、「まずは書いてみること」を大事にしてみてくださいね。
中学受験に向いている子の特徴を伸ばすために家庭でできるサポート法

お子さんが中学受験に向いているかどうかが気になる保護者の方は多いと思います。
「向いているかも」と感じたら、その特徴をもっと伸ばしてあげたいですよね。
また、「うちの子はちょっと向いていないかも……」と感じている方も大丈夫。
ご家庭でのサポートによって、子どもの力を引き出し、グッと成長させることは十分に可能です。
ここでは、中学受験に向いている子の特徴をさらに伸ばすために、家庭でできる具体的なサポート方法をご紹介します。
ちょっとした工夫や声かけが、子どもにとって大きな励みになることもあります。
ぜひ、できることから取り入れてみてくださいね。
「この学校に行きたい!」と思える目標を一緒に考える
中学受験に向けたサポートで大切なのは、まず「目標づくり」です。
親が一方的に決めるのではなく、子どもが「この学校に行ってみたい!」と心から思えるような志望校を、一緒に話し合って見つけていきましょう。
目標がはっきりすると、「どうしたら合格できるか?」を子ども自身が考えるようになり、自然と勉強へのモチベーションも高まります。
志望校を考えるときには、偏差値だけでなく、こんなポイントもチェックしてみてください。
・興味のあるクラブ活動があるか
・学校の雰囲気や校風は合いそうか
・自分に合った授業スタイルか(アクティブラーニング、少人数制など)
学校説明会や文化祭に足を運び、実際の学校の様子を一緒に見ることも、とてもおすすめです。
「ここに通いたい!」という気持ちを一緒に育てていくことが、受験へのやる気につながります。
自発的に勉強できる環境を整える
中学受験に向けて、自分から進んで勉強できるような「環境づくり」もとても大切です。
ここで大事なのは、2つの視点から整えること。
それは、「①:物理的な環境」と「②:心理的な環境」です。
①:物理的な環境を整える
勉強する場所や道具が整っていると、「勉強しよう」という気持ちが自然と高まります。
たとえば……
・勉強する場所を決める(子ども部屋より、リビング学習が向いている子もいます)
・机の上には必要なものだけを置く(文房具や教材の定位置を決めておくと◎)
・スマホやタブレットの使い方にルールを作る
こうした工夫をすることで、勉強に集中しやすい空間をつくれます。
②:心理的な環境を整える
「やる気が出る仕掛け」も家庭で意識してみましょう。
たとえば……
・勉強時間を決めて、毎日の習慣にする(朝15分の漢字練習、塾後10分の復習など)
・「今日やること」を見える化する(付箋やホワイトボードで管理するのもおすすめ)
・小さな成功体験を増やす(「漢字テスト満点だったね!」など、努力をしっかり認める)
保護者の方も一緒にスケジュールを決め習慣化したり、子どもの努力や過程、結果を認めたりすることがとても大切です。
こうした心理的なサポートがあると、子どもは「次もやってみよう!」という気持ちになりやすくなります。
環境づくりは、親子で一緒にできる受験サポートの第一歩です。
日常のやり取りを通して知的好奇心を刺激する
「知的好奇心」は、もともと備わっている子だけのものではありません。
ちょっとした日常の声かけや体験の中で、少しずつ育てていくことができるんです。
子どもは教科書で学ぶよりも実際に体験する方が記憶に残りやすいもの。
科学館や博物館に一緒にでかけたり、旅行を通じてお城や歴史に触れてみるのもいい方法です。
プログラミングやロボット工作などでは、論理的思考を育てるのに最適で、遊び感覚で学べるので数学が好きになる子も多くいます。
また、毎日の会話の中でもできることはたくさんあります。
・「今日こんなニュースがあったよ」と話題をふってみる
・「なぜ雨って降るんだろう?」など、こちらから問いかけてみる
・子どもが質問してきたときに、すぐ答えず「一緒に調べてみようか」と導いてみる
子どもからの質問が少ない場合は、こちらから「なぜ?」を考えさせる質問をしてみるのもいいですね。
このように「考える習慣」を積み重ねることで、だんだんと「知ることが楽しい!」「考えるって面白い!」という気持ちが育っていきます。
知的好奇心は、特別な教材や塾だけで育つものではありません。
毎日の会話や、親子のちょっとした体験の中に、その芽がたくさんあるんですよ。
子どもを励ます声かけで「やる気」を引き出す
中学受験は長い道のりです。時には思うように結果が出ず、子どもが落ち込んでしまうこともありますよね。
そんなときに大切なのが、保護者の方からの声かけです。
ただ「頑張ってね」と言うだけではなく、子どもが努力したことに目を向けた言葉をかけてあげましょう。
「毎日コツコツ続けててえらいね。」
「昨日より漢字がスラスラ書けるようになってるね!」
「最後まであきらめなかったの、すごいと思うよ。」
このように「結果」ではなく「過程」に注目することで、子どもは自信を持ち、努力を楽しめるようになります。
また、失敗したときも「なんでできなかったの?」ではなく、
「どこでつまずいたのかな?一緒に見てみようか!」
「間違えたってことは、そこを覚えたらまた一歩前進だね。」
と前向きな声かけをしてあげると、子どもは「チャレンジしていいんだ」と感じられるようになります。
ポジティブな声かけは、子どものやる気と自己肯定感を育てる大きな力になりますよ。
感情のコントロール力を育てる工夫
受験期は、どうしてもプレッシャーや不安を感じやすい時期です。
とくに本番が近づいてくると、焦りや緊張、イライラなど、さまざまな感情に揺れることも増えてきます。
そんなときに必要なのが、「自分の気持ちに気づいて、落ち着く力」=感情のコントロール力です。
この力は、親子の関わりの中でも育てることができます。
たとえば……
・「今どんな気持ち?」と声をかけて、自分の感情に気づかせる
・落ち着かないときは、深呼吸を一緒にして気持ちを切り替える
・うまくいかない日も「そんな日もあるよ」と受け止める
感情の起伏があること自体は悪いことではありません。
大切なのは「気持ちを切り替える経験」を重ねること。
お気に入りの文房具を使う、音楽を聴く、好きなおやつで気分転換するなど、リラックスの方法を一緒に見つけておくと安心ですね。
保護者があたたかく寄り添いながら「失敗しても大丈夫」「立て直せるよ」と伝えていくことで、子どもは少しずつ感情をうまく扱えるようになっていきます。
中学受験の対策はいつから始めるべき?

中学受験は、始めるタイミングもとても大切です。
「いつから始めるのが正解?」と迷う保護者の方も多いのではないでしょうか。
ここでは、中学受験対策を始める時期の目安や、早く始めることのメリット・デメリットを解説します。
小学3年生の終わりごろから始める子が多い
中学受験の準備は、一般的に小学3年生の終わりごろから始める家庭が多く見られます。
受験に向けた勉強は、範囲が広く、思考力や記述力を問う特殊な問題も多いため、しっかりと対策するにはおよそ3年かかるともいわれています。
そのため、4年生から本格的な受験勉強をスタートできるよう、3年生の終盤には「学習習慣をつける」「勉強への抵抗感をなくす」といった準備を始めておくことが大切です。
中学受験の対策を早めにスタートするメリット・デメリット
中学受験の勉強は、早く始めたほうが良いというイメージを持つ方も多いかもしれません。
しかし、早ければいいというものでもなく、メリットとデメリットの両方を理解しておくことが大切です。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 基礎学力がしっかり固まる | 受験までの期間が長くなり、モチベーションが下がる |
| 受験勉強に余裕をもって取り組めるので、精神的に安定しやすい | 低学年から塾に通うと費用がかさむ |
| 知的好奇心を育てられる | 他の習い事や遊ぶ時間が減ってしまう |
早くから始めることで、受験までにゆとりをもって勉強することができます。
「基礎→応用→実践」と、段階的にしっかりと学ぶことができ、一気につめこむよりも理解が深まるでしょう。
模試の成績も安定しやすく、勉強している子どもの自信にもつながることが大きなメリットです。
しかし早くから受験勉強を始めることによって、受験までの期間が長くモチベーションが下がってしまうというデメリットもあります。
周りの子が遊んでいる低学年の時期からずっと勉強をしていると、遊ぶ時間が少なくてストレスが溜まったり、スポーツなどの他の習い事を続けられなくなったりもします。低学年から塾に通うと、家計にも大きな負担になってしまうということも。
特に低学年のうちは「遊び」や「さまざまな経験」もとても大切です。
受験勉強と両立できるよう、無理のないペースで取り組み、子どもがのびのび過ごせる時間も大切にしてあげましょう。
入塾のタイミングはどう決める?
中学受験に向けた塾選びでは、「いつから通わせるべきか?」と悩む保護者の方も多いですよね。
一般的な進学塾では、小学3年生の2月(新4年生のタイミング)から中学受験用のカリキュラムが始まります。
塾での3年間の学習の流れは以下の通りです。
・小学4年生:基礎学力を固める(小学校の内容を先取り)
・小学5年生:中学受験に必要な範囲の学習を一通り終える
・小学6年生:応用問題や志望校別の対策を中心に取り組む
このように、4年生からスタートできると、余裕を持って段階的に学習が進められます。
一方で、5年生や6年生からの入塾を検討する場合は注意が必要です。
進度が速い集団塾では、学年が進むにつれて途中からの受け入れが難しくなることもあります。
その場合は、以下のような方法も視野に入れてみましょう。
・個別指導塾(子どものペースに合わせて学べる)
・家庭教師(完全にオーダーメイドの指導が可能)
遅めのスタートでも、子どもに合った学び方を見つけることで十分に中学受験に対応できます。
無理に焦らず、子どもの性格や学力に合わせた学習スタイルを選びましょう。
麗澤瑞浪中学・高等学校の入試情報

2020年に開校60年を迎えた麗澤瑞浪中学・高等学校は、「知徳一体の教育」を基本理念とし、「深く関わらなくても生きていける時代に、誰かと共に生きられる強い心を育てる」ことにこだわりをもって教育に取り組む中高一貫校です。
「おはよう」から「おやすみ」までを学びと考え、中学から入学する人、高校から入学する人と、全国各地から生徒が集まるこの学校では半数の生徒が寮生活を送っています。
ここでは、麗澤瑞浪中学・高等学校の入試概要や特徴、過去問の入手方法をご紹介します。
入試の概要と特徴
麗澤瑞浪中学・高等学校の入試は、1期試験と2期試験があり、1期試験は「学科重視型」「自己アピール型」の2通りの受験方法があります。
1期試験の2つの方式
| 方式 | 内容 |
|---|---|
| 学科重視型 | ① 学科試験(下記いずれかを選択) ・国語・算数 ・国語・算数・理科 ・国語・算数・理科・社会 ② 個人面接 |
| 自己アピール型 | ① 学科試験(国語・算数) ② 自己アピール面接 ③ 個人面接 |
いずれの学科試験も、小学校の教科書をしっかりと学び、授業をきちんと受けていると解ける問題が出題されます。
またどちらにもある個人面接では、きちんと整った日本語で話し、自己アピールがしっかりとできることが重要です。
自己アピール型で受験する場合は、自己アピール面接という特別な面接があります。
・口頭発表
・実技発表
・読書プレゼン
・英語スピーチ
この4つの内容のどれにするかをあらかじめ申請しておき、事前に提出した申請書に基づいて面接が行われます。
アピール時間は約3分、その後質疑応答の時間は約5分ほどあります。
実績や資格を重視する面接ではなく、伝え方やその熱意でプラス面を評価する面接です。
2期試験の特徴
・学科試験:適性検査①【国/算 基礎学力】 (30 分:50 点) / 適性検査② 【国/算/理/社の総合問題】 (30 分:50 点)
・面接:集団面接+個人面接の2回(面接は受験者のみ)
集団面接では「答えのない問い」がテーマに出され、昨年は「最近あったちょっとした幸せ」について話し合いました。
仲間を尊重しながら自分の意見を伝える力が問われます。他人の意見を否定せず、よく聴いて発言する姿勢がポイントです。
1期2期ともに、面接に重きを置いた試験といえます。事前に面接対策をしっかりしておくと良いですね。
▷詳しくはホームページの「受験生の方へ」ページをご確認ください。
過去問の入手方法
麗澤瑞浪中学校の入試を検討している方は、過去問を活用して対策を進めるのがおすすめです。
過去問は【資料請求】という形でお申し込みいただけます。以下のフォームよりお申し込みください。
▷過去問請求フォームはこちら(※麗澤瑞浪中学・高等学校の資料請求フォームページに飛びます)
郵送でのお届けとなりますので、早めのご請求がおすすめです。
まとめ:中学受験は『向いている子』だけのものじゃない!サポート次第で伸びる

中学受験に向いている子には、いくつかの特徴があります。
でも、「うちの子は当てはまらないから無理かも…」と受験を諦める必要はありません。
実際には、家庭でのサポートや環境の工夫によって、子どもの可能性は大きく伸ばせます。
むしろ家庭でのサポート次第で「受験に向いている状態」に近づけることができるのです。
・目標を見つける手助けをする
・自分から勉強しやすい環境を整える
・知的好奇心を育てる
・子どもを励ます声かけで「やる気」を引き出す
・感情のコントロール力を育てる工夫
この5つを意識して、自分の子どもにあった受験の形を見つけていきましょう。
中学受験をすること自体が子どもの成長にもつながるもの。
中学受験は、ただ合格を目指すだけでなく、「学ぶ楽しさ」や「努力する力」を育てる良い機会でもあります。
お子さんの性格や個性を大切にしながら、無理のないペースでチャレンジできるように、保護者の皆さんがそっと背中を押してあげてください。
\中学受験をお考えのご家庭へ/
麗澤瑞浪中学校では、小学6年生を対象とした入試イベントを複数開催します。
志望校選び・準備にぜひお役立てください。
-
終了:【10月4日(土)】入試対策&入試勉強会
国語・算数の勉強会では在校生もサポートに参加。グループワークで「みんなで考える」楽しさを体感できます。保護者向け奨学金説明・個別相談会も同時開催。
※来校形式/9:00受付開始・寮見学あり
終了しました▶ イベントに申し込む終了【11月15日(土)】プレテスト&学校説明会
実際の入試に近い形式で模擬試験を実施。合格可能性の判定・レーダーチャート返却あり。保護者対象の説明会・キャンパスツアーも同日開催。
※本校・東京・自宅受験から選択/8:30受付開始・参加無料
終了しました▶ プレテストに申し込む終了【9〜12月】個別見学会(小学4年生以上)
土日祝に教職員がマンツーマンで校舎・寮をご案内。他の参加者と一緒にならず、じっくり見学・相談が可能です。オンライン参加や瑞浪駅からの送迎も対応。
※来校 or オンライン/事前予約制
終了しました▶ 見学会に申し込む